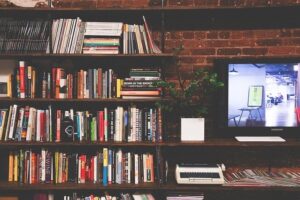正月になると新春という言葉が至る所で使われますよね?
個人的にパッと思いついたものだとデパートなどでの『新春初売りセール』などと使われていたりもしますが、イメージ的には昔から使われている言葉であるようにも思えます。
また、『初春』とニュアンスも近いので、意味的にも似ているもののようにも思えます。
【関連記事】
正月になるとこの新春という言葉を目にする機会が多くなりますが、実際の意味や期間について詳しくは知らなかったので、色々と調べてみた事をまとめてみました!
<スポンサーリンク>
新春とはどういった意味?
新春とは『新年』の事を表す言葉となっており、正月にあちこちでよく使われていますよね。
他にも似たような言葉として
・迎春(げいしゅん)
・頌春(しょうしゅん)
・賀春(がしゅん)
などといった言葉があります。
これらの言葉にはだいたい同じような意味合いが含まれていますが、用途によって使い分けたりするようです。
例えば、頌春や賀春といった言葉に関して言えば、年賀状などに用いられて書かれていたりもします。普段は使いませんが、年賀状を書く際によく目にするのではないでしょうか?
それぞれ新年を称えたり祝ったりする際に用いられているので、日本に住んでいる生粋の日本人であれば、年に一度は見る事になるかもしれません。
<スポンサーリンク>
新春はいつからいつまでの期間?
新春〇〇セールなどといった宣伝文句で正月にあちこちで使われていますが、実際の所いつまで使う事が出来るのでしょうか?
先ほども述べましたが、そもそも新春という言葉の意味としては、新年や正月を表す言葉となります。
なので基本的には1月中に使われる事になってきます。
2月に入ってから新春と言う言葉は見られなくなるようになりますので、大方イメージが付きやすいかなと思われます。
そこで、正月について再び述べますと、基本的には正月は三が日の事を表しています。
なので、1月1日~3日までは正月となりますが、正月飾りなどをする松の内という期間があり、これに関しては1月7日、もしくは関西では15日までとなっているようです。
【関連記事】
また小正月が元々は15日までとされていたので、この頃までが正月として扱っても良い期間であるとも言えるでしょう。
そもそも昔の基準として、旧暦では1月中は正月であるとも呼ばれていたようなので、本来の意味としては1月中であれば新春という言葉は使い続けても良かったのかもしれません。
ただ、15日くらいになってくると徐々にその言葉自体も町中では聞かなくなってきますので、具体的にいつまで使って良いという事はありませんが、15日くらいまで使っていても本来の意味から考えても特に問題は無さそうです。
元々は旧暦がベースとなっているという事もありますし、その名残りとして現在まで受け継がれているという事を念頭に考えておくと良いでしょう。
まとめ
日本の文化は旧暦から新暦に受け継がれている所があり、旧暦の名残りとして言ってしまえば昔とはズレが生じてしまいます。
そういった意味でも具体的にいつまでという事は決められる事は出来ませんので、自分が住んでいる地域に合わせてみたりするのが無難になってくるのでしょうね。
ただ、目安としては1月7~15日くらいまでが新春という言葉を使えるものだと思っていても良いかもしれませんね。
<スポンサーリンク>