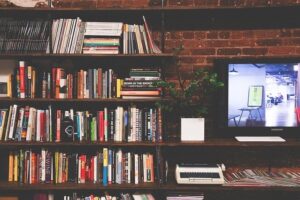『初春』と言うと、あなたはどのような日の事をイメージされるでしょうか? 「春先の事?」「一年の初め?」など、なんとなく始まりや春の訪れをイメージさせるような感じがしています。
また、同じ「春」の漢字が付いている言葉として『新春』がありますが、それについてはコチラの記事にまとめています。
【関連記事】
この記事では、『初春』の由来や意味について調べた事をまとめてみました。
<スポンサーリンク>
初春の読み方。意味
まず、初春について辞書で調べてみると、
【読み方】
=しょしゅん、はつはる
【意味】
=春の初め。正月。新年。新春
と書かれています。
いずれも、新たな始まりや出発を連想させそうなイメージがしますね。どこか初々しさもあるように思えます。
また、初春の同じような意味の言葉として『孟春(もうしゅん)』がありますが、こちらも同じような意味として使われているようです。
ところで、『春の初め』とはいったいいつぞやの事を指すのでしょうか?
「梅の花?それとも桜の花が咲くころ?」
「春の陽気が感じられたとき?」
「2月3月くらい?」
と、漠然とではありますが、個人的にはそのような印象がありました。
ですが、具体的に初春が「いつからいつまで?」という事に関してはちょっとややこしいようですね。。
初春はいつからいつまで?
そこで調べてみると、初春とは旧暦正月である旧暦の一月の別称となっているみたいです。明治時代に入ってから現在の新暦に変わり、旧暦とは30~40日のズレが生じた結果、現在に至るとの事です。
なので、そういった事実を踏まえて言えば初春とは、『新年早々』の意味を表しており、一年の始まりを告げる言葉として使われていたとされています。
と、ここで旧暦の正月を現在の暦に当てはめてみた場合ですと、現在では2月4日頃の立春(節分の次の日)から3月6日頃の啓蟄の前日に当たるようです。今では1月1日の日から正月となっているので、現代の感覚からしてみたら違和感がありますよね。^^;
実際にはいつまでという決まりはあまり無いようにも思われますが、意味としてはお正月辺りとなるようです。
<スポンサーリンク>
「初春」を使った挨拶・例文
初春という言葉を使った挨拶として、『初春の候』という言葉があります。
読み方は
初春の候=「しょしゅんのそうろう」「はつはるのこう」
となっています。
音読みと訓読みがありますが、どちらでも意味としては同じなので、どちらを用いても構わないとの事ですね!
この初春の候の意味に関してはと言うと、先ほども述べたように、初春には新春や春の初めといった意味に加え、『候(そうろう)』は天候や気候といった意味となっています。
ちなみに、『初春』の箇所を『新春』『大寒』『寒冷』として使うことも出来、『候』に関しては『折』または『みぎり』を使う事も出来ます。
以上の事をまとめると、
・新春のこの良き日に
・いよいよ新しい年を迎え
など、このような挨拶の例文の一部分として使う事が出来ます。
(参考・引用元)
『きちんと知っておきたい 大人の冠婚葬祭マナー新辞典』岩下宣子 監修 朝日新聞出版
まとめ
最後に「初春」についてまとめると以下のようなものとなりました。
・初春とは、旧暦正月である旧暦の一月の別称
・「春の初め」「正月」「新年」といった意味がある
といったものとなります。
昔の暦と現在の暦とで見比べてしまうとズレが生じてしまい、具体的にいつまでなのかという事が漠然としていて分かりづらいですよね。
また、旧暦と新暦の違いがあったりと、過去をさかのぼる事によって、現在に当時の名残として残されている風習というのは、個人的にとても興味深く思えてしまいます。
<スポンサーリンク>