一年の最後の日となる12月31日の大晦日。
歳を重ねていく毎に、一年があっという間に過ぎてしまうように感じてしまいますが、この日に今年一年を振り返る良いきっかけともなります。
特に大晦日という日は普段の日と違い、どこか厳かな雰囲気があり、いつもと違う特別な一日であるように感じてしまいますよね。
「あと数時間で新しい年が始まる…」
そう考えると、どこかしみじみと感じてしまうかもしれません。
数日前にはクリスマス気分であったものの、今年も残すところあと僅かとなり、師走の慌ただしかった日々もひと段落つくところでしょう。
新年を迎えるにあたって節目となる一日となる大晦日ですが、この大晦日の由来やこの日にやることについて、調べてみたことをまとめました。
<スポンサーリンク>
大晦日の「晦日」の意味や由来について

旧暦では毎月、最後の日の事を「晦日(みそか)」と呼ばれていました。
例えば1月の最後の日も「晦日」と呼ばれますし、同様に4月、8月など、どの月の最後の日も「晦日」となっています。
中でも12月31日は「大晦日(おおみそか)」と呼ばれ、一年を締め括るべく各々思い思いに過ごす日となっています。
【補足】
みそかの「みそ」という言葉は「30」という意味もあり、その為みそかは30日という意味で使われていました。
たとえば、30歳の事を「三十路(みそじ)」と呼ばれていますね。
また、一般的に使われる事はあまりないかもしれませんが、大晦日の別名を「大つごもり」とも言われています。
この「つごもり」というのは「月隠り(つきごもり)」が語源となっているようです。
元々の旧暦では、一年の最後の日は12月30日だったという事もあり、この日が晦日と呼ばれていました。
しかし、年によっては29日であったりと、日にちが変動する年もあったようですね。
そして新暦となった際に12月31日がその年の最後の日となったため、今では12月31日が「大晦日」であるという事が一般的に定着する事となりました。
<スポンサーリンク>
大晦日の文化
日本では歳神様を迎える日となっており、それにちなんだ行事が行われています。
例えば下の項目でも書かれている年越しそばを食べたり、日本各地の寺院で除夜の鐘を鳴らすといった風習がありますね。
あるいは年徳様に対する信仰心が元となった日本独自の儀礼であるとも言えます。
この年徳様というのは、節分の際に恵方巻を食べる際の神様がいる方角ともなっています。
大晦日の日にすること
年越しそばを食べる

日本には大晦日に年越しそばを食べる風習があります。
細く長いそばに健康長寿や家運長寿を願うという願いが込められており、縁起を担ぐという意味で食べられています。
この風習というのはさかのぼる事、江戸時代から続いていると言われています。
年越しそばを食べる時間帯は地域によってまちまちで、大晦日の日の夕方に食べる地域もあれば、年越しの日付が変わると同時に食べるところもあるようです。
個人的には「大晦日に年越しそばを食べないと新年を迎えられない」と思ってしまうほど根付いている風習だと思わされますね。
<スポンサーリンク>
二年参り
あまり聞きなれない言葉ではありますが、二年参りとは初詣の一つの形式でもあり、大晦日の日の深夜0時をまたいで神社仏閣に参拝する事となっています。
新年を迎える前に一度参拝し、一旦家に帰り、日付が変わった後の元旦の日にもう一度参拝(初詣)する事となっています。
除夜の鐘

日本各地の寺院にある梵鐘(ぼんしょう)と呼ばれる大きな鐘をつき、午前0時を挟んで108回鐘を鳴らす事となります。
この108回というのは、人間の持つ煩悩(ぼんのう)の数といわれています。
年末の大晦日の深夜0時近く鐘を鳴らして煩悩を追い払い、新年を清らかな気持ちで迎えられるようにします。
また、除夜の鐘は大晦日に108回鳴らすものだと思われがちではありますが、正しくは年内のうちに107回鐘をつき、108回目は年が明けた後につく事となります。
クイズ番組などのひっかけ問題として出題される事もあるようですね。笑
【補足】
「除夜」には眠らない夜という意味もあります。
かつては大晦日の晩に神社にこもって年を越すという事から「年籠り(としこもり)」という風習が昔にありました。
そのため、大晦日の事を「除夜」と呼ぶようになったようです。
家族と一緒に過ごす

家族団らんで一緒に過ごす一日でもあります。
普段は実家を離れ、遠く離れて暮らしている人でも、年末年始のこの時期は実家に里帰りするという方も多いのではないでしょうか?
それぞれ思い思いの一年を過ごし、年末のこの時期に親戚・家族一同集まって年末年始のテレビ番組を皆で観る事でしょう。
一方で最近は核家族や単身化が進み年末年始を一人で過ごすという方も年々増えていたり、年末年始も変わらず仕事の予定が入っていたりするなどといった背景もあるようです。
年越しを家族や誰かと一緒に過ごすという予定が仮に無かったとしても、インターネットが繋がっていれば人と繋がっている感覚もあるかもしれません。
特に予定が無い場合はあらかじめアルバイトを入れておいたりするなど、年末年始を過ごす方法は多様化しております。
SNSで一年を締め括る挨拶など
SNSの発達に伴い、今年一年お世話になった方々やフォロワーに向けてメッセージを呟く人も居る事でしょう。
必ずしもやるという訳ではありませんが、どちらかと言えば自発的に発信するという方も多いようですね。
これは年末だから特別という訳でもなく、SNSがすでに生活の一部となっている方々にとっては当たり前のような感覚なのかもしれません。
逆に言えば、やらないと気が済まないといったところかもしれません。
また、年末の年の瀬に使う挨拶についてこの記事でまとめています。
上司など目上の人や日頃からお世話になっているという方々にも、感謝の意を込めて失礼の無いように一年を締め括りたいものですからね。
大晦日のテレビ番組

紅白歌合戦や、年越しライブ、ガキ使など、大晦日にしかやらない特別番組が編成されています!
・大晦日紅白歌合戦
・ダウンタウンのガキの使いやあらへんで
・CDTVスペシャル!年越しプレミアムライブ
・ゆく年くる年
・大みそか列島縦断LIVE
・ジャニーズカウントダウン
・ドラえもん大晦日スペシャル
など、他にもボクシングやその年に話題になったドラマのディレクターズカット版など、ラインナップは充実しています。
近年、テレビ離れが加速する一方ではありますが、この日だけは家族揃ってテレビを観るという方も少なからず居る事でしょう。
特に2018年の紅白歌合戦は平成最後の紅白という事もあり、近年観た中でも盛り上がり具合が凄かったですね!
最高視聴率45.3%3という数字を叩き出したサザンオールスターズの桑田さんとユーミンのコラボ。
5年ぶりに紅白に復帰したサブちゃんこと北島三郎さんや話題になった米津幻師さんなど、豪華歌手の方々が盛り上げてくれました。
これによって、来年以降の紅白歌合戦のハードルも上がってしまったかもしれませんが、1951年(昭和26年)から続く国民的音楽番組でもあるので、今後の紅白も期待していきたいところでもあります!
まとめ
大晦日の日にすることや、その由来、文化についてまとめました。
一年を締め括る最後の一日となる大晦日。それぞれ新年を迎えるにあたって思い思いに過ごす一日でもある事でしょう。
<スポンサーリンク>



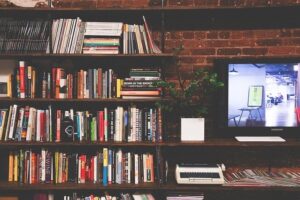



















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。