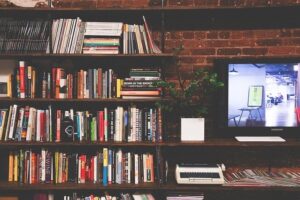日本では、お正月になると鏡餅を飾る習慣があります。
毎年、各家庭で飾られている方もいられる事でしょう。
とはいえ、いつまでも家に飾っているわけにもいきませんよね!
食用の餅でも作った鏡餅ですし、やはり食べ物を粗末にするのはもったいないという事もありますから。。
そこで下げた鏡餅を皆で食べる事となりますが、この日の事を鏡開きの日と言い、毎年お正月恒例の日本の伝統行事ともなっています。
また、俳句の季語としても用いられているので、文学作品を学ぶ際に用いられて使われているかもしれません。
それでは、鏡開きの意味や由来、日にちについて調べた事をまとめていきますね。
<スポンサーリンク>
鏡開きとは?
鏡開き(鏡割り)とは、正月に神様や仏様にお供え物をする鏡餅を下げ、その後お雑煮やお汁粉などにして食べる事となっています。

なぜ鏡開きをするのかと言うと、供えられていた鏡餅に力が宿ると言われております。
それ食べる事によってこの一年を病気やケガに見舞われる事無く無事に過ごす事を願う風習となっているのですね。
そしてその際に神仏に対して感謝を伝え、無病息災を祈る日となっています。
鏡開きの由来・意味
鏡開きは日本の伝統行事として古来より受け継がれていますが、その由来はどこからきているのでしょうか?
そこで調べてみた所、鏡開きの由来となったのは江戸時代となっているようです。
「鏡」は円満を意味し、「開く」は末広がりを連想させるという事で縁起の良い意味となっています。
さらに鏡餅は固い為、それを食すことで歯を丈夫にして長寿を祈るという意味も込められています。 これを「歯固め」と呼びます。(実際には煮込んだりして食べるのですが)
鏡開きの日にち
鏡開きは一般的に1月7日の松の内が終わった後での1月11日に行われます。
しかし、地域によって日程が変わってくる事もありますので、必ずしも11日に行われるという訳でも無いようですね。
なぜなら、お正月の飾りを飾っておく「松の内」の期間が地域によって異なっているという事もあり、それに合わせて鏡開きの日も変わってくるという事となっています。
大きく2つに分けると、関東の松の内は1月7日までに対して、関西は15日まで行うとされています。
地域によって日にちが違う理由
地域によってなぜ日にちが違うのかと言いますと、かつては旧暦の1月20日に鏡開きが行われていたとされています。
1651年。当時の将軍徳川家光が亡くなった日が4月20日となってしまったため、1月20日を忌日として避ける事がきっかけとなりました。
その後は松の内の日の後に鏡開きを取り決め、現在に至った経緯があるようです。
何かと縁起の良いものを良しとする国民性でもありますので、こうした忌日となる日を避けたがるようですね。
しかし、一方でその事が関西方面まで広まらなかった為、現在においても関東と関西の鏡開きの日が違う理由となっています。
その為、それぞれの鏡開きの日をまとめると、
関東・・1月11日
関西・・1月20日
となっています。
また、京都など一部の地域では1月4日に鏡開きを行う地域もあるようですね!
これは正月3が日が終わった直後に鏡開きをする風習があったため、京都が日本で一番早い鏡開きとなっているようです。
<スポンサーリンク>
鏡開きのやり方。食べ方
鏡開きをする際、実はやってはいけない事があります。
一般的には手や木づちで餅を割る事となりますが、刃物で鏡餅を割る事は絶対にいけません!!
良い例〇
悪い例×

これには理由があり、刃物で割る事と言うのは「切腹」を連想させる事となってしまい、避ける必要があります。
また、「切る」「割る」といった言葉は印象の悪いイメージを連想させてしまうため、「開く」と言われるようにもなりました。
正月に縁起の悪い事で祝いたくありませんからね^^;
なのでこの点は注意しておく必要があります!
なお、一部の地域では木づちで割った際に餅が多く割れた場合、その一年豊作に見舞われるという事もありますので縁起が良いと言われています。
2019年の鏡開きはいつ?
これは前項でも述べたように、2019年の鏡開きの日は1月11日となっております。
関西も同様に1月20日となっているようです。
基本的には日程に変わりは無いと思われるので、来年の2019年以降も同じであると思っても良いでしょう。
鏡開きについてのまとめ
不慮の事故等に遭わなくても済むように、日本人は一年の健康を祈るため、神仏の力を受けて無病息災を祈る国民とも呼べます。やはり健康第一ですから。
自分も含め家族や親しくしている方らの健康も祈っていきたいですよね! お餅をおいしくいただいて良い年になるように願いましょう!
[amazonjs asin=”B002D5VVMG” locale=”JP” title=”ミニ鏡開きセット 祝”]
<スポンサーリンク>