寒い冬が終わり、ようやく暖かな日差しが差し込んでくる季節の変わり目になると立春が訪れる事となります。
この立春という言葉に関して言えば耳にした事があるという方は多くいられるかと思われますが、詳し意味についてご存知でしょうか?
この記事ではそんな立春についての疑問を解消するべく、気になって調べたものについてまとめてみました!
2022年(令和4年)以前、以降の日付についてもまとめているので、そちらも併せてご覧頂けると幸いです。
<スポンサーリンク>
立春とは?

立春とは、一年を24分割した際の分割点を含む日に季節の名称を表す二十四節気のうちの第1となっています。その年によって若干の誤差がありますが、2月4日前後が立春となっています。
これはなぜかと言いますと、太陽の角度が変わってくるため、年度によっては2月3日、あるいは2月5日が立春となる事もある為です。
また、現在広まっている二十四節気を配置する方法の一つとされる定期法によると、太陽黄経(太陽の角度)が315度である際に2月4日が立春となっています。
立春の行事
節分
立春に関しては上記にまとめましたが、では立春には何をする必要があるのか?という事についても調べてみました。
まず、上記でも述べたように、立春は年度によって変動がありますが、それがおおよそ2月4日となっています。
この日の前日というのは節分となっており、無病息災を願って豆まきをしたり、福を呼び寄せる為に恵方巻を食べる日となっています。
【関連記事】
昔であれば立春は正月に近いという事に加え、徐々に温かくなって春が待ち遠しくなる季節であるものでした。長く寒い冬が終わり、ようやく春の訪れを感じる。そんな1日だったとも言えますね。
立春大吉
立春の早朝になると禅寺では門に「立春大吉」という書した紙を貼るという習慣があります。
この立春大吉というのは、左右対称の為、文字を逆の方向から読んでも同じ漢字になります。そのことから、万が一家の中に悪い鬼が入り込んだとしても家の中なのに外にいるような錯覚をさせ、そのまま鬼を外に追い払ってしまう厄除けにもなりえるものです。
何かと縁起が良いものを好む日本人の性質として、謹賀新年と同様におまじないの意味も込めてこの立春から一年間の間に厄災や災難に遭わないようにするための厄除けであったとされています。
また、禅寺に限らず民家の家々でも同様に、柱などに半紙に墨で「立春大吉」と書かれたモノを貼るといった方法もあるようです。
<スポンサーリンク>
2022年の立春の日付
2022年の立春の日付けは2月4日(金)となっています。
2022年前後の立春の日付
その年の前後のデータを見ると、定期法によるとその年によって日付がその都度異なります。2022年の前後の立春の日付けに関しては、以下の日付となっています。
【立春の日付】
・2017年(平成29年)・・・ 2月4日(土)
・2018年(平成30年)・・・ 2月4日(日)
・2019年(令和 元年)・・・ 2月4日(月)
・2020年(令和 2年)・・・ 2月4日(火)
・2021年(令和 3年)・・・ 2月3日(水)
・2022年(令和 4年)・・・ 2月4日(金)
・2023年(令和 5年)・・・ 2月4日(土)
・2024年(令和 6年)・・・ 2月4日(日)
・2025年(令和 7年)・・・ 2月3日(火)
・2026年(令和 8年)・・・ 2月4日(水)
・2027年(令和 9年)・・・ 2月4日(木)
さらに過去を遡ってみてもほとんどの立春の日付けが2月4日となっていましたが、1984年に関しては立春の日付けが2月5日となっていました。ちなみに、前年の2021年の立春は2月3日となっています。
立春が2月3日、あるいは2月5日となる年はそう滅多に無いようなので、およそ2月4日頃といった表現で表される事が多いようです。
まとめ
立春は祝日でもないので、特に気にせずに過ごしてしまう事もありがちです。ですが、この時期を境に梅の花が咲くなど徐々に春の兆しが見えてくる季節でもあるので、ある意味立春を心待ちにしている方もおられるかもしれませんね。
徐々に春の訪れを感じつつ、外出する機会が増えてくるような時期であると言えます。
<スポンサーリンク>

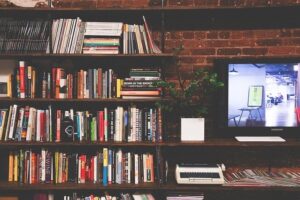




















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。