5月に入りますと慌ただしかった新生活もひと段落し、徐々に落ち着きだす時期でもある事でしょう。
3連休のゴールデンウィークも控え、この時期になると各イベント会場では盛り上がりも見せていますね。
しかし、どこも込み合っているため、外出するよりも自宅で趣味に没頭したり好きな事をするという人もいるかもしれませんね。
ただ一方で五月病という言葉もあるように、ゴールデンウィーク明けの登校・出勤する際に鬱々とした気分が晴れないなど、正式な病名では無いものの体調が優れずやる気も起きない症状が現れてしまう時期でもあるかもしれません。
貴重な連休ではありますが、連休明けと同時に現実とどう向き合っていけるかも考える必要があるかもしれませんね。
この記事では、5月の行事・イベントについてまとめました。
何かしら参考にしていただけると幸いです。
<スポンサーリンク>
5月の行事・イベント
メーデー(5月1日)
メーデーとは、世界各地で毎年5月1日行われる「労働者の日」となっています。
「メーデー=May Day」となっており、直訳すれば「五月の日」となります。
本来は五月祭を意味していましたが、今日では旧東側諸国では労働者が統一して権利要求と行進などを取り行う日としている国もあるようです。
八十八夜(5月2日ごろ)
八十八夜とは、立春から数えて88日目にあたる日の事を指します。
あまり馴染みのない言葉ではありますが、唱歌『茶摘み』の「夏も近づく八十八夜~」の出だしで歌われている言葉でもあるので、聞いた事があるという方もいるかもしれません。
この時期になりますと柔らかく質の良い茶葉が摂る事が出来るという事もあり、さらに末広がりの「八」という漢字もかけて縁起物であるとされています。
また温かな気候となり、作物・穀物を育てるのに適した時期でもあります。
憲法記念日(5月3日)
憲法記念日とは、1947年(昭和22年)に日本国憲法が施行された日を記念し、定められた国民の祝日の一つとなっております。
五月の大型連休でもあるゴールデンウィークのうちの一日でもありますね。
みどりの日(5月4日)
大型三連休の二日目となるみどりの日。
1989年に第125代天皇が即位し、2007年に5月の3連休に移動するまでは4月29日となっていました。
子供の日、端午の節句(5月5日)
三連休最終日の5月5日はこどもの日となっています。
現在では「子供の日」となっていますが、季節の変わり目である五節句の一つとして端午の節句となっていました。
菖蒲(しょうぶ)で邪気を払うなど、鎌倉時代に入ってからは「菖蒲」と「尚武」(武道を重んじる事)とをかけて男の子の節句として祝われていたようです。
そして子供の日になると子供の成長を願い、鯉のぼりをあげたり五月人形を各家庭に飾ったりします。


我が家でも子供の頃にリビングに五月人形が飾られておりました。
学校から帰宅すると兜と鎧が飾られており、子供ながらにうれしかった記憶があります。
ちなみにこの五月人形のモデルとなったのは金太郎となっており、彼のように力強く健やかに成長を願うといった思いが込められています。
立夏(5月6日ごろ)
立夏とは、二十四節気の穀雨の次に当たる第7となっています。
春分と夏至の中間で、春から徐々に夏の気配がし始める時期となっています。
<スポンサーリンク>
母の日(第2日曜日)
母の日になりますと、日頃お世話になっている母に対して感謝の意を込めてカーネーションや喜ばれる贈り物などをします。
贈り物として定番はカーネーションではありますが、アクセサリーやグルメギフトなども贈り物として最適です。
母の日は元々はアメリカが発祥でしたが、次第に日本にも伝わるようになったのは大正時代と言われています。
また他の国でも同様に母の日は制定されていますが、国によって日付や起源は違うようです。
葵祭(5月15日)
葵祭り(あおいまつり)とは、京都市にある下鴨神社と上賀茂神社で行われるお祭りです。
京都三大祭りの一つで、他にも祇園祭(7月)、時代祭(10月)があります。
三社祭(5月第三週金・土・日)
三社祭とは、浅草神社の氏子四十四ヶ町を中心に、第三金・土・日の三日間にわたって行われる日本を代表する祭礼の一つとなっています。
見どころは3機のお神輿となっており、町中を周ります。
小満(5月21日ごろ)
小満は、二十四節気の立夏の次に当たる第8となっています。
麦畑が緑黄色に色づき、万物が成長して一定の大きさに達する時期となります。
まとめ
5月の行事やイベントについてまとめました。
貴重な大型三連休のある5月をどのように有意義に過ごせるかは各々次第ではありますが、充実した日々を送れると良いですね。
<スポンサーリンク>



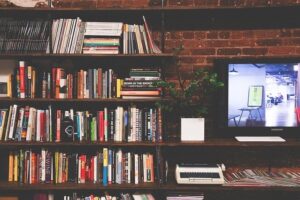



















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。